蚤の市の読み方と意味!語源と由来や世界での呼び名は?
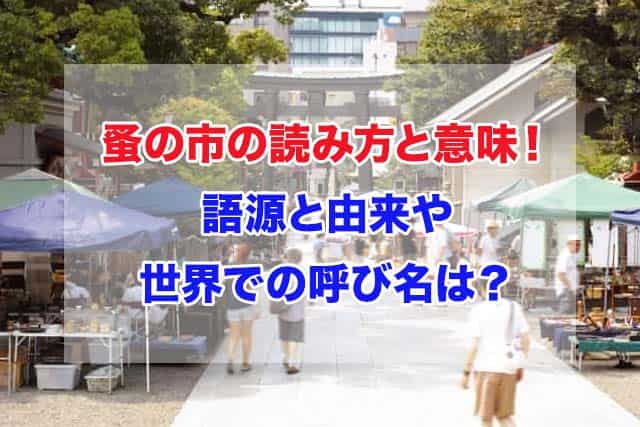
街中のポスターや新聞のチラシなどで目にすることも多い蚤の市という言葉。
実は、読み方や意味はあまり知られていません。
蚤の市を利用されている方でも、語源や由来を知っている人は少ないかもしれませんね。
また、中国や韓国、ヨーロッパ各国など、世界での呼び名も調査してみましたよ!
確認しておくと、海外旅行に行かれる際に役立つ可能性もありますね。
そこで今回は、蚤の市の読み方と意味!語源と由来や世界での呼び名は?というテーマでご紹介しますね。
スポンサーリンク
蚤の市の読み方
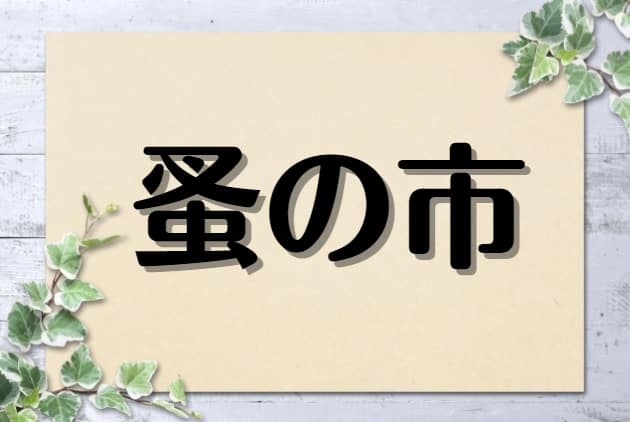
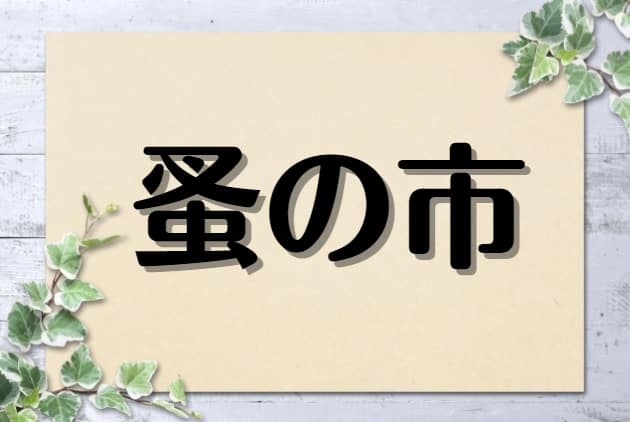
まず、蚤の市の読み方は「のみのいち」です。
「蚤」の字の読みには、以下のようなものがあります。
- 訓読み:「のみ」「つめ」「はや(い)」
- 音読み:「ソウ」
また、「市」は「いちば」のように人が集まって売買や交易をする場を表す、訓読みの「いち」が使われています。
「蚤の市」に構成が似た言葉として「酉の市」「年(歳)の市」などが有名ですね!
蚤の市の意味


蚤の市の意味は、古着をはじめとする使用済みの商品を扱う「古物市」のことです。
年代物のジーンズ、バッグ、アクセサリー、時計、手作りの小物入れなど、様々な品が売り買いされています。
品揃えはほぼ無数といった印象で、販売されていない古いネジや画びょうなども見かけます。
蚤の市はヴィンテージ品の収集家や、日常生活で使える物を安く購入したい人にも人気ですね!
同義の言葉として「ガラクタ市」「ボロ市」「フリーマーケット(フリマ)」などがあります。
現在では「フリマ」と呼んだ方が意味が通じやすいと思われます。
スポンサーリンク
蚤の市の語源


蚤の市の語源は、フランス語の「marché aux puces(マルシェ・オ・ピュス)」とされています。
単語それぞれの意味は、以下の通りです。
- marché(マルシェ)=市場
- aux(オ)=「~の」「~入りの」「~に」「~で」を表す前置詞
- puces(ピュス)=昆虫の蚤
つまり、もともとフランス語でも「蚤の市」ということになります。
英語では直訳で「flea market(フリーマーケット)」となっていますが、日本への伝来は以下の2通りの説があります。
- フランスで柔道の指導していた石黒敬七氏が直訳で日本に伝えた
- 英語の「flea market」が外来語として伝わり、蚤の市と訳された
どちらが先だったのかは曖昧でハッキリしていません。
個人的にはずっと「free(自由)」だと思っていましたが、蚤を意味する「flea」だったとは驚きでした。
蚤の市の由来


蚤の市は、1800年代後半にフランス・パリで「シフォニエ(ゴミ拾い)」と呼ばれていた貧しい人々に由来します。
彼らはゴミの中から売れそうな品を選別し、商いを行って生計を立てていました。
しかし、彼らはパリの大規模改革により街中にいられなくなり…
仕方なくパリ郊外のサン=トゥアンに移動し、商いの拠点を作りました。
当時のサン=トゥアンはパリ・ティエールの城壁より外側だったため、何もない場所だったといわれています。
街を追われたシフォニエたちはヴィラ(バラック)を建てて、古物の売り買いを再開しました。
その場にはゴミや古物、ガラクタが山積しており、「蚤の市」と呼ばれるようになりました。
もともとは衛生状態が悪く、蚤が湧くような環境を蔑(さげす)む言葉だったのかもしれません。
現在では「クリニャンクールの蚤の市」と呼ばれるようになり…
世界最大規模の3000店のショップが並ぶ、オシャレで人気の観光スポットとなっています。
蚤の市の由来となったシフォニエたちがいなかったら、今人気のフリマは存在していなかったかもしれませんね!
スポンサーリンク
蚤の市の世界での呼び名


最近では、神社の参道、公園、スポーツ施設の駐車場などでもよく見かける蚤の市。
世界での呼び名も気になりましたので、以下にまとめてみました。
| 国名 | 蚤の市の呼び名 | カタカナ表記 | 蚤を表す言葉 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 跳蚤市场 | ティアォヅァォシィーチァン | 跳蚤(ティアォヅァォ) |
| 韓国 | 벼룩시장 | ピョルクシジャン | 벼룩(ピョルク) |
| ドイツ | Flohmarkt | フローマルクト | Floh(フロー) |
| オランダ | vlooienmarkt | フローインマルクトゥ | vlo(フロー) |
| イタリア | mercato delle pulci | メルカート デッレ プルチ | pulce(プルチ) |
| スペイン | mercado de pulgas | メルカード デ ポルガス | pulga(ポルガ) |
| ロシア | Барахолка | ボラホールカ | блоха(ブロッハ) |
日本と同様、世界各国でも蚤の市ではなく、フリーマーケット由来の別の言葉もあります。
また、蚤を表す言葉にも単数形や複数形などが使用されており、各国で使い分けされているようです。
スポンサーリンク
蚤の市の読み方と意味!語源と由来や世界での呼び名は?のまとめ
- 蚤の市の読み方は「のみのいち」
- 本来の意味は使用済みの商品を売買する「古物市」
- 語源はフランス語の「marché aux puces(マルシェ・オ・ピュス)」
- 英語では直訳で「flea market(フリーマーケット)」
- 由来はパリで「シフォニエ(ゴミ拾い)」と呼ばれた貧しい人々が始めた市
- 現在では「クリニャンクールの蚤の市」と呼ばれ、フランスの人気スポットとなった
- 蚤の市の世界での呼び名にも昆虫の蚤が使われている
蚤といえば、人やペット、家畜などに寄生し、吸血してひどい痒みを及ぼす小さな害虫です。
確かに古い物から湧き出てきそうなイメージですが、「蚤の市」や「フリーマーケット」の語源だったとは驚きでしたね!
家族や友人などでも知らない人は多いと思いますので、ぜひ豆知識として教えてあげてくださいね。

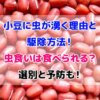

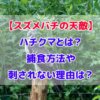

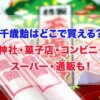

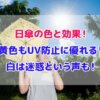

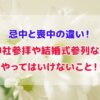

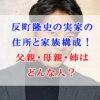
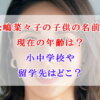
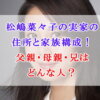
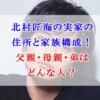

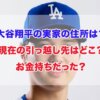

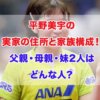
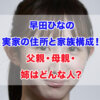
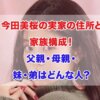
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません