正月飾りはいつからいつまで飾る?門松・しめ飾り・鏡餅は?

12月も上旬を過ぎると、正月飾りの準備を始めるご家庭も多いと思います。
主に、門松、しめ飾り、鏡餅が挙げられますが、いつからいつまで飾るのかご存じですか?
あまり早過ぎても世間体が気になりますし、年の瀬に慌てて用意するのも避けたいですね。
正月飾りにはそれぞれ飾る期間の目安がありますので、それに習って飾ることをおすすめします。
そこで今回は、正月飾りはいつからいつまで飾る?門松・しめ飾り・鏡餅は?というテーマでご紹介します!
スポンサーリンク
そもそも正月飾りとは?


そもそも正月飾りとは、新年を祝う意味で飾られる様々な縁起物のお飾りのことです。
昔から、門松、しめ飾り、鏡餅の他、床の間飾り、掛け軸、生花、破魔矢、羽子板などなどを飾る習慣がありました。
現在では、毎年1月1日に各家庭に来訪される、年神様を迎えるための飾り物を呼んでいます。
代表される正月飾りは、門松、しめ飾り、鏡餅のみとなりましたが、ぞれぞれが年神様の依り代として大切な役割を持っています。
門松


門松は、松竹梅を中心に葉牡丹、南天、熊笹などをあしらった豪華な飾り物で…
家の門や玄関の前、オフィスの入り口前などに飾られることがほとんどですね!
新年の幸福をもたらすために降臨される年神様は、門松を目印として各家庭に入られます。
2本で一対のものは、左側にクロマツを使った「雄松」を、右側にアカマツを使った「雌松」を設置します。
年神様を迎え入れるための依り代なので、門松は最も重要な正月飾りといっても過言ではありません。
別名として「松飾り」「飾り松」「立て松」などと呼ぶこともあります。
しめ飾り


しめ飾りは、穂が出る前の稲を乾燥させた藁を編んで作る「しめ縄」の一種です。
主に、裏白(ウラジロ)、楪(ユズリハ)、紙垂(シデ)などで飾り付けをします。
年神様の依り代というより、神の領域と現世の境界を示す「結界」として意味合いが強いです。
家の中を神聖で清浄な領域と変えるため、しめ飾りには厄や禍を祓う効果があります。
主な種類として「ゴボウ締め」「輪飾り」「大根締め」「一文字」などがあります。
鏡餅


鏡餅は、鏡に見立てた大小2段の丸餅を重ねて作る、年神様への供物の1つです。
昔は青銅製の丸い鏡を使っており、すべてを映し出す鏡はこの世とあの世の境目と捉えられていました。
また、ハレの日に食べるお餅を使った鏡餅は、穀物神でもある年神様の依り代として大きな役割を持っています。
正月期間が明けるまで年神様は鏡餅の中に宿り、役目を終えると御魂を残して帰って行かれます。
年神様の御魂は「年玉」とも呼ばれ、鏡餅を食べることで1年を生き抜くパワーを授かることができます。
また、大小2段の鏡餅は月と太陽、陰と陽を表し、夫婦円満を祈願する正月飾りといわれています。
スポンサーリンク
正月飾りはいつから飾る?


本来、正月飾りは12月13日の「正月事始め」から飾るものとされています。
「お正月に向けた準備を始める日」という意味で、この日には煤払いなども行われていますね。
そのため、12月13日から飾ってもよいのですが、「さすがに早過ぎる」という人も多いです。
というのも、日本でもクリスマスを祝うようになってから、状況が変わってきています。
街中がクリスマスムード一色なのに正月飾りを飾るのは気が引けますので…
以下に相応しい日取りをまとめてみました。
門松はいつから飾る?


門松を飾るのは、クリスマスが終わった12月26日以降が一般的です。
12月26日、27日、28日、30日が相応しいとされています。
ベストな日取りは末広がりの8が付く12月28日で、縁起の良さからもおすすめです。
逆に、縁起が悪く相応しくないのが12月29日と31日(大晦日)で、理由は以下の通りです。
【12月29日】
- 数字の9を含む日に門松を立てるのは「苦立て」を意味する
- この日に飾る門松は「九松」と呼ばれ、「苦待つ」に通じる
- 29という数字から「二重苦」を連想させる
【12月31日】※大晦日に飾ることを「一夜飾り」といいます
- 一夜飾りは葬儀と同じ飾り方になるため縁起が悪い
- 準備期間が短すぎるのは誠意に欠けるため、年神様に対して失礼に当たる
- 新しい年神様が降臨されるのは大晦日なので、前年の年神様との引継ぎが間に合わない
※年神様は1年間家の中に滞在されるという考え方もあります
忙しくて門松を設置する時間がないという場合でも、12月30日までに飾れば問題ありません。
しめ縄はいつから飾る?


しめ飾りに関しては、門松と全く同じ期間に飾るものとされています。
そのため、正月事始め以降に飾っても問題ありません。
クリスマス以降にしたい場合は、12月26日、27日、28日、30日に飾ります。
ベストな日取りはもちろん12月28日になります。
鏡餅はいつから飾る?


鏡餅の場合、あまり早く飾るとカビが生える心配がありますよね。
正月期間中も飾っておくことを考えると、12月28日と12月30日が最もオススメです。
餅つきを行う日との兼ね合いもありますが、あまり早過ぎない方がよいでしょう!
最近ではプラスチック製の鏡餅のオブジェや、中に切り餅などが入ったタイプもありますよね。
生のお餅を使っていない場合は、門松と同じ日取りにするとよいですね!
スポンサーリンク
正月飾りはいつまで飾る?


続いて、正月飾りはいつまで飾るのか、見ていきましょう!
基本的に、門松、しめ飾り、鏡餅はそれぞれで飾り納めの日が決まっていますので、あまり悩むこともありません。
ただし、注意事項として、地域によって片付ける日取りが異なる点が挙げられます。
門松としめ飾りはいつまで飾る?


前述した通り、門松としめ飾りは飾る期間が全く同じなので、飾り納めの日も同じです。
どちらも、松の内と呼ばれる期間内は飾っておけますが、明けてしまったら片付けてしまいます。
【松の内】
- 関東:1月1日~1月7日(※東北や九州など大多数を占める)
- 関西:1月1日~1月15日
関東を含む日本の多くの地域では1月7日まで、関西では小正月に当たる1月15日まで飾ります。
それぞれ、翌日となる1月8日、1月16日には早々に片付けてしまうことが多いです。
また、正月の祝い納めとされる二十日正月を重んじる地域では、1月20日まで飾る所もあります。(群馬・石川・岐阜ほか)
沖縄の場合、正月に引き続き旧正月を祝う習慣がありますが、旧正月は旧暦に基づくため、新暦でははっきりいつまでと決まっていません。
鏡餅はいつまで飾る?


鏡餅に関しては、全国的に1月11日の鏡開きまで飾っておくことがほとんどです。
関西の鏡開きは1月15日、または1月20日に行う地域もあるといわれています。
関西の中でも京都では1月4日に鏡開きを行いますが、昔の朝廷の影響ではないかと思われます。
正月の三が日が終わってすぐなので、ほかの地域の人からするとビックリですね!
まとめ
正月飾りを代表する門松、しめ飾り、鏡餅は、地域によって飾っておく期間が決まっています。
そのため、あれこれ迷う心配はないかと思われます。
ただし、関西は文化の違いにより、松の内や鏡開きの日取りも異なってきます。
結婚や転勤などを機に初めて関西で正月を迎える方は、ギャップを感じるかもしれませんね!


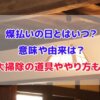
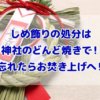


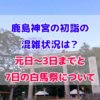
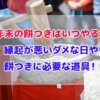

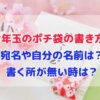

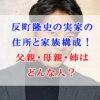
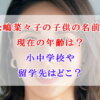
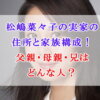
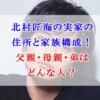

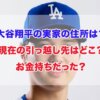

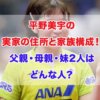
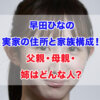
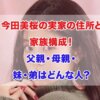
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません